DISEASE DETAILS 疾患一覧
肘の痛み
異所性骨化(Heterotopic ossification)
異所性骨化(Heterotopic ossification)は、リハビリテーションの場において頻繁に見られる合併症で、通常は骨が存在しない軟部組織や筋肉の中に骨ができることです。新しく骨ができた部位の痛み、腫れ、熱感、関節の動きの制限がでます。関節では、肘と股関節に多いことが知られています。
打撲などの外傷後に発生する骨化性筋炎(Myositis ossificans)は、異所性骨化の最も一般的なタイプです。

異所性骨化(骨化性筋炎)の原因
骨化性筋炎には、外傷性と非外傷性の原因があります。外傷の既往があるものは、60%から75%との報告があります。急速に増大するため、特に非外傷性の場合、悪性腫瘍と間違われることがあります。このため、「偽悪性骨腫瘍」と呼ばれることもあります。
好発年齢は、思春期から青年期にかけてで、肘、大腿部、殿部などに発症することがあります。脊椎損傷後の麻痺がある場合、外傷部位とは関係なく、股関節や膝関節に認められることが多くなります。
外傷以外では、遺伝や手術後、または手や足の指に明らかな原因なく発症する反応性の骨化など、様々な原因があります。他にも、動脈硬化や脊椎・関節周辺の靭帯の骨化も異所性骨化の一部です。
限局性骨化性筋炎(または「myositis ossificans circumscripta」とも言われます)は、原因が不明であるか、外傷後に生じる異所性骨化の一例です。臨床でよく遭遇し、腫瘍との鑑別が必要とされることがあります。
異所性骨化(骨化性筋炎)の症状
最も多い症状は、痛みと可動域(関節が動く範囲)の減少です。しばしば関節のこわばりもでます。他によく見られる症状としては、局所的な浮腫、熱感、および組織や関節の圧痛があります。局所的な軟部組織の腫れは、深部静脈血栓症(DVT)のように見えることがあり注意が必要です。微熱が出ることもあります。とくに痛みがある状態で無理に運動を繰り返すと悪化しやすく、安静加療が非常に重要です。
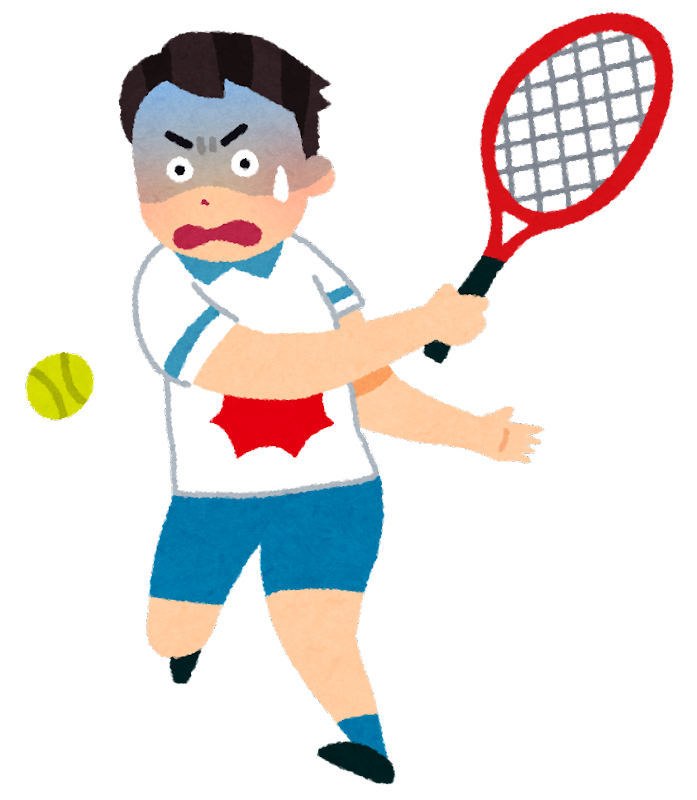
異所性骨化(骨化性筋炎)の検査
血液検査ではALP(アルカリフォスファターゼ)の上昇を認めます。初期には上昇しないことがあり、上昇するまでに最大2週間かかり、外傷後10週間で正常値の3.5倍まで上昇することがあります。ALPは、長骨の損傷が関連している場合に偽高値となることもあります。
赤血球沈降速度(ESR)やCRPも炎症反応として参考になります。クレアチンキナーゼ(CK)は異所性骨化の重症度を判定するために使用され、脊髄損傷患者18人の研究では、上昇したCKがより強い症状と関連し、かつエチドロネート療法への抵抗性の可能性を示すことが判明しました。
単純X線撮影では、関節の周囲または近くに円環状の骨形成が示されます。X線は初期骨化が移りにくいこともあり、bone scanに異所性骨化が現れてから3週間から4週間経ってからでないと陽性にならないことがあります。CTは、骨形成の領域を明確に判断することができ、3D構築もでき、ほかの疾患の除外にも有効です。
異所性骨化(骨化性筋炎)の予防
予防法としては愛護的なROM(可動域)訓練、インドメタシン、エチドロネートなどの薬剤があります。また、痙攣性などのリスクファクターを管理することも重要とされます。インドメタシンは予防に最も一般的に使用されるNSAIDです。メロキシカム、セレコキシブ、ロフェコキシブ、イブプロフェンなど、効果が証明された他のNSAIDもあります。
エチドロネートは、脊髄損傷および全股関節置換術の合併症における異所性骨化の予防に承認されたビスホスホネートという骨粗しょう症の薬です。本邦では異所性骨化の予防のための使用は一般的ではない印象です。
異所性骨化(骨化性筋炎)の治療
多くの病変は鎮痛薬の処方や安静などの保存的治療だけで自然に小さくなったり、消失します。
リハビリは可動域の改善のために有効ですが、無理な他動訓練は症状を増悪させるリスクがあるので、自動運動を中心に、疾患に対する知識のある理学療法士が担当します。
成熟した骨化病変に対してはインドメタシン系NSAID、エチドロネートの投薬が有効です。
関節可動域が制限されたり、血管や神経の圧迫症状が出る場合は、手術を検討します。術後の再発を避けるため、発症後6か月以内の骨化形成期が過ぎて、骨化が成熟した時期に手術を行うことが推奨されています。
参考文献)
・今日の整形外科治療指針 第8版.
・JRRD, Volume 51 Number 3, 2014. Pages 497-502. Management of multijoint stiffness of bilateral upper limbs secondary to heterotopic ossification: Case report and literature review
・Heterotopic Ossification.Eric Sun; Aaron A. Hanyu-Deutmeyer.
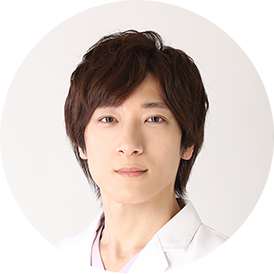
先生から一言
異所性骨化が診断されないまま、無理な運動や整骨院での施術によって痛みや可動域制限が悪化することが度々あります。
疾患知識のある専門医を受診し、早期診断を受けることが後遺症を残さないために重要です。
