DISEASE DETAILS 疾患一覧

肩の痛み
肩関節拘縮
肩関節拘縮は、「関節包や靭帯などの軟部組織が硬くなることによる関節の可動域制限」を指します。特に肩関節はもともとの動きが大きいぶん、硬くなりやすいとされています。
肩関節拘縮の原因となる疾患や病態
肩関節拘縮をきたす疾患には様々な病態が含まれます。いかにその例を示します。
1. 肩関節周囲炎
40歳から60歳の人々の間で、明らかな外傷がないにもかかわらず生じる有痛性の関節拘縮を「肩関節周囲炎=五十肩」と呼んでいます。しかし、「五十肩」の概念はまだ明確ではありません。さらに、凍結肩、肩関節周囲炎、癒着性肩関節包炎など、さまざまな病名が存在します。肩関節周囲炎は、中年以降に加齢などに伴う退行性変化を基盤として発生する、有痛性で関節可動域制限を伴う疾患です。「五十肩」「凍結肩」「癒着性関節包炎」と呼ばれることもあります。女性や非利き手側に多くみられ、20%の患者さんが両側に罹患します。二次性の場合の多くは糖尿病性であり、うつ病が原因となることもあります。肩関節周囲炎は、急性期(freezing phase)、拘縮期(frozen phase)、回復期(thawing phase)の3つの病期に分けられます。急性期では、強い痛みがあり、安静時痛や夜間痛を訴えることがあります。このため、運動が制限されることが多いです。拘縮期では、肩関節の拘縮が進行し、全方向に可動域制限が生じますが、特に外旋や外転の制限が顕著です。回復期では、徐々に可動域制限が改善していきます。
肩関節周囲炎は、腱板断裂やインピンジメント症候群とは可動域制限のパターンが異なります。肩関節周囲炎では全方向に可動域が制限されますが、腱板断裂やインピンジメント症候群では挙上(屈曲、外転)の制限が主となります。自然治癒の傾向はありますが、20~30%の患者さんでは後遺症として軽度の拘縮が残る場合もあります。
2. 痛風・偽痛風
痛風や偽痛風では、局所に熱感、発赤、腫脹を伴い、運動が制限されます。治療には非ステロイド系抗炎症剤が使用され、通常1~3日で痛みが軽減し、1週間程度で消失します。ステロイド薬は、非ステロイド系抗炎症剤が無効な場合に使用されます。関節液の検査では、偽痛風の場合はピロリン酸カルシウム結晶が、痛風の場合は尿酸ナトリウム結晶が認められます。
3. 上腕二頭筋長頭腱炎
上腕二頭筋長頭腱炎では、肘関節を外旋・屈曲する際に、上腕二頭筋腱が通る上腕骨の結節間溝に痛みが生じ、圧痛が認められます。診断のためにはYergasonテストやSpeedテストが行われます。
画像診断では、MRI検査や超音波検査で腱の肥厚や高信号が確認されます。痛みが強い場合には、結節間溝へのステロイド注射が行われることがあります。
4. 石灰沈着性腱板炎
石灰沈着性腱板炎は中年に好発し、女性にやや多く見られる疾患です。原因はまだ明らかになっていません。急性期には、腱内の浮腫を伴う容量の増大が炎症を引き起こし、急激な肩の痛みを訴えることが多いです。他動運動が制限され、X線検査では石灰化が確認されます。
治療には、非ステロイド性抗炎症剤の投与、ステロイドと局所麻酔剤の注射、さらには石灰洗浄回収(パンピング)が行われます。
5. 腱板損傷
腱板損傷は、肩甲上腕関節に付着する腱板筋の腱性部分が断裂する疾患です。中高年に多く見られ、退行変性や肩峰との機械的衝突(インピンジメント)、外傷が原因となります。腱板損傷には完全断裂(全層断裂)と不全断裂(部分断裂)があり、不全断裂はさらに滑液包面断裂、腱内断裂、関節面断裂に分類されます。
症状としては痛みや挙上障害などの機能不全が見られますが、無症状のケースも少なくありません。視診や触診で棘下筋の筋萎縮が確認されることがあります。
診断にはMRI検査が有用です。診察テストとしては以下の方法が行われます。
- Neerテスト:肩甲骨を固定しながら他動的に外転させ、90°以上で痛みが出れば陽性です。
- Hawkinsテスト:肩関節を90°屈曲させ、他動的に肩を内旋した際に痛みが出れば陽性です。
- Painful arc sign:外転60°付近から痛みが生じ、120°付近で痛みが消失する場合に陽性とされます。
- Drop arm sign:検者が他動的に上肢を90°外転させ、その状態を保てずに上肢が下垂する場合に陽性と判断されます。
治療は、痛みが軽減した後に肩甲胸郭関節や肩甲上腕関節へのストレッチ、腱板機能訓練などのリハビリテーションを行います。手術は主に鏡視下で実施されています。
6. 脳卒中の後遺症
脳卒中を発症した後に上肢を動かさずにいると、肩関節包が徐々に狭くなり、結果として肩関節の可動域が制限されることがあります。特に片麻痺の患者さんでは、肩関節の痛みとともに、関節の可動域、なかでも外旋や外転の動きに制限が生じることが多く、これらの要素には相関があるとされています。また、肩関節の造影検査では、癒着性肩関節包炎の所見が認められる場合もあります。
脳卒中患者さんにおいて拘縮が起こる原因には、いくつかの要素が挙げられます。まず、上肢を動かさないことによって関節周囲の軟部組織が短縮し、柔軟性が失われることが一因です。さらに、脳卒中後には筋緊張の異常な亢進が見られることがあり、これが痙性拘縮を引き起こすことがあります。加えて、不適切な動作の繰り返しや訓練によって関節や筋に過度な負担がかかることで、二次的に拘縮が生じることもあります。また、循環障害による浮腫により、関節周囲の軟部組織が柔軟性を失うことも拘縮の要因となります。
特に注意が必要なのは、長期間にわたって三角巾やアームスリングを使用することや、移乗動作の際に肩関節を損傷してしまうことです。これらも拘縮を引き起こす重要な要因となり得ます。脳卒中患者さんでは、麻痺側だけでなく、非麻痺側にも関節可動域の制限が生じることがあり、とくに麻痺側ではより強い制限が現れる傾向があります。Shimadaらの研究によれば、脳卒中による片麻痺患者さんにおいて、拘縮が最も多く認められる部位は肩関節であると報告されています。
肩関節拘縮のメカニズム
凍結肩という病気は、肩の関節を構成するやわらかい組織――たとえば、関節を包む膜(関節包)、その内側を覆う滑膜、そして肩の動きを支える腱(腱板)など――に何らかの変化が起こり、それに対して体が防御反応を示している状態だと考えています。
関節包や靭帯については、以前からコラーゲンというたんぱく質が増えることが知られています。特に、肩の奥にある「腱板疎部」や「烏口上腕靭帯」と呼ばれる場所では、組織が硬くなったり、変性したりすることがあります。前方の関節包では、傷が治るときに多く作られる「タイプIIIコラーゲン」が見られ、組織が新しく作られていることが示されています。また、TGF-βやPDGFなど、組織を硬くする働きのある物質(成長因子)が関与していることもわかっています。
音の振動を使って組織の硬さを調べる「音響顕微鏡」で見ると、凍結肩では関節包が硬くなっており、細胞が多く集まっていることがわかります。炎症や組織の硬化(線維化)、さらには軟骨のような成分ができてくるような反応に関わる遺伝子も活発に働いていることが確認されています。また、この関節包の変化は、手のひらの腱が縮んでしまう「デュピュイトラン拘縮」という病気とよく似ている点があり、実際に関節の一部には「筋線維芽細胞」という特殊な細胞が見つかっています。
関節の内側を覆う「滑膜」については、特に症状が強く出始める時期(Freezing phase)に、細胞の数が増え、炎症に関係する物質――たとえばTNF-αやIL-1、IL-6など――が多くなっていることが調べられています。症状が落ち着いてくる時期(Frozen phase)では、関節包の中に線維芽細胞という細胞が増えているものの、組織の修復や再生に必要な酵素(MMP-14)は足りていないことも報告されています。このような中で、肥満細胞やリンパ球、マクロファージといった免疫の細胞も見られ、肩の中では慢性的な炎症が起こっていると考えられています。
これらの研究結果から、凍結肩は、滑膜に炎症が起こってそれが長く続き、TGF-βなどの物質によって関節包のコラーゲンが増え、痛みで肩を動かさなくなることで、関節が徐々に固まって動かなくなる――という流れで進行すると考えられています。
画像検査からわかることとしては、関節の造影検査で関節の中のスペースが狭くなっていたり、脇の下にある「腋窩陥凹(えきかかんおう)」と呼ばれるくぼみが小さくなっていたりすることが確認されます。また、肩の奥にある滑液包(関節のクッション)がふさがっていることもあり、こうした所見は関節包が短くなっていることを示しています。
MRI検査でも、脇の下の関節包が厚く、短くなっているのがわかります。さらに「ダイナミックMRI」という造影剤を使った検査では、病気の進行に伴って関節の滑膜の炎症が落ち着き、それに伴い画像上の反応が弱くなっていく様子が観察されます。関節に増えた血管の映像も確認されており、肩関節の血流が増え、炎症が続いている状態であると考えられます。
凍結肩、肩関節拘縮の治療
特発性肩関節拘縮(凍結肩)の治療には、物理療法、運動療法、内服療法、注射療法など、多角的なアプローチが必要で、病期や症状、生活背景を踏まえて選択することが重要です。また、治療効果には個人差があるため、長期的なフォローアップと必要に応じた治療の見直しが求められます。万人に対して有効な治療方法は医学的に確立していません。
腱板断裂や上腕二頭筋長頭腱炎など、基礎疾患がある場合は、まずその原因に対する治療を考慮する必要があります。凍結肩の治療を始めるにあたり、病期の理解は非常に重要です。病期は、疼痛が主体の「炎症期」、関節拘縮が主となる「凍結期」、可動域が改善していく「解凍期」に分けられ、それぞれに応じた治療が求められます。
保存療法には、消炎鎮痛を目的とした物理療法、ストレッチを中心とする運動療法、内服療法があります。注射療法には、肩関節内または肩峰下滑液包内への注射、関節腔拡張法、超音波下神経ブロックなど、さまざまな手法があります。難治性の場合は手術療法を検討しますが、ここでは手術以外の治療法について説明します。
物理療法:炎症期では、疼痛と炎症の軽減を目的として、冷却療法、パルス波による超音波療法、電気刺激療法が有効とされています。凍結期以降では、関節可動域の改善を目的に、温熱療法(連続波超音波療法や超短波療法)や電気刺激療法が使用されますが、これらに関する体系的な報告は限られています。
運動療法:炎症期では、安静の確保と肩関節の過伸展を防ぐことが大切です。振り子運動や他動運動など、負荷の少ない運動が有効です。凍結期には、可動域訓練やストレッチを積極的に取り入れます。過去の研究では、週2回の振り子運動や他動的ストレッチによって、疼痛軽減と可動域の改善が認められていますが、改善には一定の期間を要する傾向があります。
内服療法:一般的には、副作用の少ないNSAIDsが使用されます。ステロイドの内服療法も有効とされ、炎症の抑制と可動域改善が期待されます。ただし、ステロイドは保険適用外であるため、投与方法や副作用への配慮が必要です。
注射療法:注射療法は、疼痛緩和と可動域改善を目的に行われます。ステロイドと局所麻酔薬の併用が一般的であり、注射部位や回数によって治療効果に差が見られる可能性があります。特に、放射線透視下での精度の高い注射は、短期間での症状改善に効果があると報告されていますが、関節軟骨への影響などについてはさらなる評価が求められます。
関節腔拡張療法(Pumping療法):関節腔拡張は、特に凍結期の可動域改善を目的に行われます。Callinanらの研究では、生理食塩水40mlにリドカイン10mlを加えて関節内に注入し、2年後の夜間痛の軽減と可動域改善が報告されています。
非観血的関節授動術(Manipulation):保存療法に効果がみられない場合、全身麻酔下で関節を動かす非観血的関節授動術を検討します。可動域の改善が得られる一方で、術前の機能と術後の改善度に明確な相関が認められないことも指摘されています。
参考文献)
・肩の障害とリハビリテーション診療. 猪飼哲夫ら. MB Medical Rehabilitation (289): 99-108, 2023.
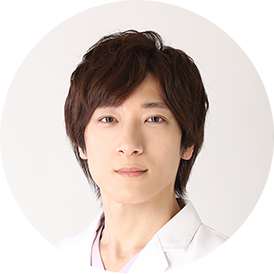
先生から一言
肩関節拘縮の治療は難渋することが多いです。疼痛コントロールを十分行ったのち、リハビリにより肩の動きを取り戻すことが何より重要です。できるだけ元の動きを取り戻せるよう、医師・理学療法士がタッグを組んで治療に当たります。3~6か月程度の保存治療を行っても改善に乏しい場合は手術を検討せざるを得ない場合もあります。
