DISEASE DETAILS 疾患一覧

肩の痛み
四辺形間隙症候群
四辺形間隙症候群(QLS)とは
肩の奥にある細い通り道「四辺形間隙」で、腋窩神経(えきかしんけい)と後上腕回旋動脈(PHCA=肩の後ろを通る血管)がこすれたり圧迫されたりして、肩〜腕に痛みやしびれが出る病気です。野球・バレーボール・水泳など、腕を頭より上に繰り返し挙げる動作で起こりやすく、症状がはっきりしないため診断が遅れることもあります。
四辺形間隙症候群(QLS)の原因
多くは神経の圧迫が原因で、外傷後の変化、筋肉の発達(肥大)、線維性の帯(きんちゃくのような膜)などが関係します。まれに、関節唇のう胞や骨折後の血のかたまり(血腫)、骨軟骨腫・脂肪腫・神経鞘腫などの“しこり”が原因になることもあります。血管のこぶ(動脈瘤)や仮性動脈瘤が背景にある例もあります。
四辺形間隙症候群(QLS)の症状
肩の奥の鈍い痛み、腕の外側のしびれ・だるさ、夜間痛、四辺形間隙付近の押して痛いところ(圧痛)がみられます。
神経が関わる場合:しびれ、筋力低下、ぴくつき(筋けいれん)など。
血管が関わる場合:手指が冷たい・青白い、脈が触れにくいなど(血流が悪いサイン)。
腕を挙げる動作を繰り返すと悪化しやすいのが特徴です。
四辺形間隙症候群(QLS)と鑑別を要すべき疾患
回旋腱板損傷、五十肩(肩関節周囲炎)、関節唇損傷、頸椎の病気、胸郭出口症候群、腕神経叢の炎症、肩甲上神経障害などと症状が似ています。脱臼や上腕骨頭骨折のあとに腋窩神経が傷むこともあるため、見分けが大切です。
四辺形間隙症候群(QLS)の検査
まず問診・触診で症状の出方や痛む場所を確認します。レントゲンで他の病気を除外し、必要に応じて超音波やMRIを行います。MRIでは小円筋などの筋肉のやせ(脂肪変性)や周囲の異常を評価できます。血管の関与が疑わしいときは、腕を外側に開いて外向きにねじった姿勢(外転・外旋)での造影検査(CT/MR血管造影や動脈造影)が役立ちます。筋電図(EMG=筋肉と神経の働きをみる検査)で、腋窩神経が担当する筋(小円筋・三角筋)の異常を確認することもありますが、陰性でも病気を完全には否定できません。
四辺形間隙症候群(QLS)の治療
まずは手術以外の保存療法が基本です。
・動作の見直し:症状が出やすいフォームや姿勢を避けます。
・理学療法:肩甲骨の安定化、可動域の改善、後方関節包・回旋筋腱板のストレッチ、必要に応じて摩擦マッサージやアクティブリリースを行います。
・薬:痛み止め(NSAIDs)や湿布を併用します。
・注射:神経の周囲に局所麻酔薬やステロイドを打つと痛みが和らぐことがあり、診断の助けにもなります。
これらで多くは改善し、痛みの軽減に合わせて段階的にスポーツ復帰を目指します(目安:数週〜数か月、種目や症状の程度により個人差があります)。
一方、6か月以上の保存療法でも痛みやしびれが続き、日常生活や競技に大きな支障がある場合は、腋窩神経の周囲の癒着や線維性の帯を取り除く減圧術を検討します。血管の関与が強い場合は、血栓を溶かす/取り除く治療や、動脈瘤に対するコイル塞栓・切除などの血管治療を選ぶこともあります。
参考文献)
・Quadrilateral Space Syndrome: Diagnosis and Clinical Management. Patrick T. Hangge
・水泳選手に生じた四辺形間隙症候群の3例. 坂口健史ら.JCHO東京新宿メディカルセンター整形外科, 2JCHO東京新宿メディカルセンターリハビリテーション科.日本臨床スポーツ医学会誌 23(4): S253-S253, 2015.
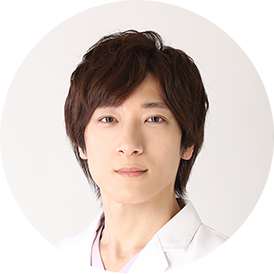
先生から一言
投球やサーブで肩の奥が痛む・しびれる、休むと軽くなるが再開で再発する、手指が冷たく色が変わる、力が入りにくいといったサインが続く場合は、早めにご相談ください。早期に原因を見極め、適切なリハビリと治療を行うことで復帰を早められます。
