DISEASE DETAILS 疾患一覧
首の痛み
頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)
頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)とは
頚椎の椎体後面を縦に走る後縦靭帯(こうじゅうじんたい)が骨のように硬くなる(骨化する)ことで、頚髄や神経根を圧迫する病気です。骨化があっても神経症状がない場合は「頚椎後縦靭帯骨化」と呼び、症状が出ている状態(OPLL)と区別します。
家族内で多い傾向があり、遺伝的素因が示唆されています。日本人では約2%にOPLLがみられ、その一部(報告により概ね1~2割)で脊髄症を発症します。初発は50歳前後に多く、男女比はおよそ2:1。糖尿病など代謝異常や全身的な骨化傾向を伴うこともあります。圧迫はゆっくり進むことが多い一方、転倒などの外傷を契機に急に悪化することがあり、頚部のけがには注意が必要です。

頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)の原因
胸椎・腰椎を含む他の部位でも後縦靭帯の骨化を伴うことがあり、遺伝因子と環境因子の双方が関与すると考えられています。肥満や糖代謝異常(糖尿病など)との関連が指摘されています。

頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)の症状
頚OPLLは、脊髄の圧迫による「脊髄症」と、神経根の圧迫による「神経根症」の原因になります。初期は無症状のこともあり、あっても頚のこりや肩甲帯のだるさ程度にとどまることがあります。
・神経根症:片側上肢の痛み・しびれ・筋力低下、支配領域に沿った感覚障害。頚を反らすと症状が誘発・増悪することがあります。
・脊髄症:手指のしびれ・巧緻運動低下(ボタンかけ、書字、箸が使いにくい)、歩行のふらつき・膝折れなどの痙性歩行。進行すると立位・歩行が困難になり、膀胱直腸障害を伴うこともあります。外傷を機に発症・増悪する例もあります。
簡易評価として「10秒テスト(両手を下に向け、10秒間でグーパーをできるだけ速く繰り返す)」が有用で、脊髄症では年齢差はあるものの概ね20回未満となります。深部腱反射の亢進やバビンスキー反射などの病的反射がみられることもあります。
頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)の検査
単純X線(側面像)で後縦靭帯の骨化を確認できますが、小さな骨化巣は見落とすことがあります。骨化の広がりや椎体との癒合の有無、占拠率の把握にはCTが有用です(再構成像で矢状断・横断像を評価)。脊髄・神経根への圧迫の程度や脊髄内変化はMRIで評価します。特にT2強調画像の脊髄内高信号は脊髄症の重症度と関連する重要所見です。正確な診断にはX線とCT、MRIを組み合わせて総合的に判断します。

MRIでは、骨化巣による脊髄や神経根への圧迫の程度を評価できます。特にT2強調画像における脊髄内高信号は脊髄症の重症度と関連する重要な所見です。ただし、骨化の有無に関してはCTに比べ診断精度が劣り、MRI単独での判定は困難です。
頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)の治療
脊髄症状を伴わず、頚部痛や神経根症を主体とする場合、あるいは脊髄症が軽度な場合には、ロキソプ脊髄症がなく、頚部痛や神経根症が主体、または脊髄症が軽度の場合は保存療法を行います。ロキソプロフェンなどの消炎鎮痛薬、プレガバリン/ミロガバリンなどによる薬物療法に加え、頚の過伸展を避ける・転倒を防ぐなどの生活指導を徹底します。装具(頚椎カラー)や頚椎牽引を用いることもあります。
日常生活に支障する脊髄症がある、症状が進行している、脊柱管狭窄が高度で強く圧迫している場合は、保存療法での改善は乏しく、手術を検討します。病態や骨化の形態に応じて、前方除圧固定術、後方除圧術、後方固定術(インプラント併用)などから選択します。

受診の目安
・手指の不器用さ(ボタンかけにくい、箸が使いにくい)、歩行のふらつき
・片側上肢の持続する痛み・しびれ、筋力低下
・転倒後に症状が急に悪化した
これらが続く場合は早めに整形外科を受診してください。
参考文献)
・頚椎後縦靭帯骨化症. 整形外科看護 29(5): 424-427, 2024.
・Lineage Medical, Inc. All rights reserved. Ossification Posterior Longitudinal Ligament.
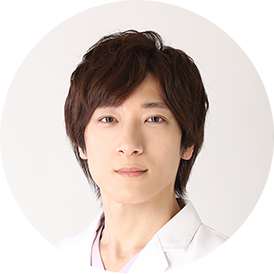
先生から一言
画像検査を適切に組み合わせて重症度を評価し、生活指導を含む保存療法から手術まで、個々の病態に合わせて治療を提案します。外傷による増悪予防も重視し、頚部の保護や転倒対策を具体的にお伝えします。
