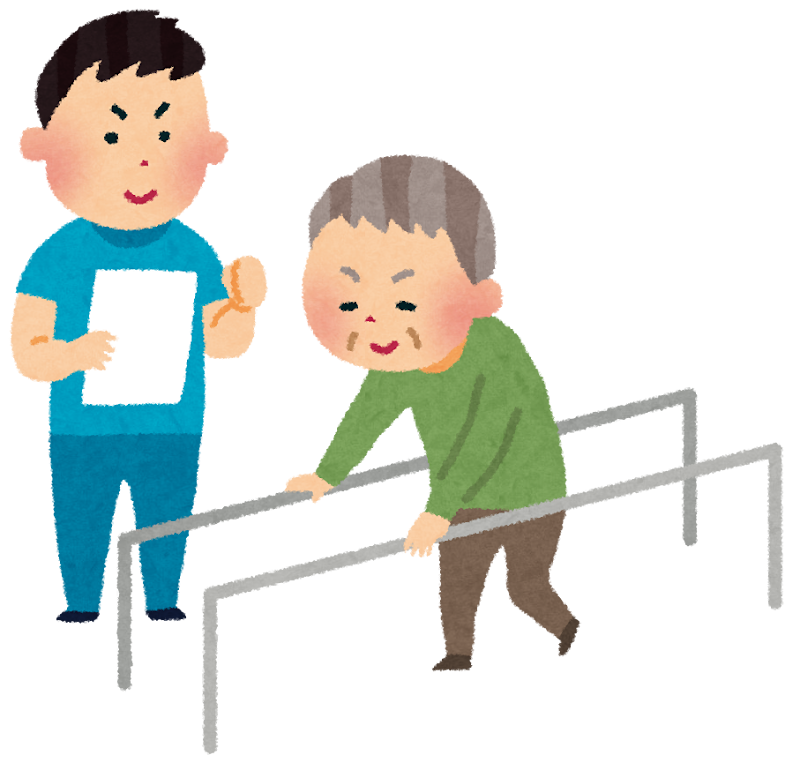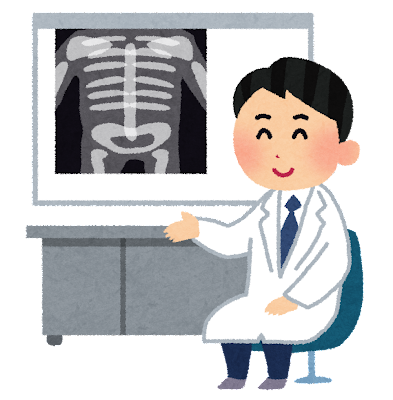BLOG ブログ
足のむくみ(下腿浮腫)の原因と治療について|受診の目安とセルフケア
みなさまこんにちは。三国ゆう整形外科の院長の曽我部です。
「夕方になると靴下の跡がくっきり残る」「足が重だるい」「片足だけ腫れている気がする」など、足のむくみはとてもよくある症状です。多くは生活習慣や血流・筋力の影響で起こりますが、心臓・腎臓・血管などの病気が隠れていることもあります。このページでは、足のむくみ(下腿浮腫)の原因、受診の目安、治療と自宅でできる対策をわかりやすくまとめます。
当院では、整形外科的な身体診察(関節・筋・腱・神経の評価)を丁寧に行い、必要に応じて超音波(エコー)で筋肉や腱、滑液包、炎症の有無などを確認します。さらに、全身性の原因が疑われる場合には血液検査の評価や適切な専門科との連携も含め、原因を見落とさないことを重視しています。症状の改善だけでなく、再発予防まで見据えて理学療法士によるリハビリテーションもご提案できます。
受診を急ぐべきサイン
次のいずれかが当てはまる場合は、自己判断せず早めに医療機関へご相談ください。
・片足だけが急に腫れた(左右差がはっきりしている)
・ふくらはぎの痛み、熱っぽさ、赤みが強い
・息切れ、胸の痛み、動くと苦しい(むくみと同時に起きている)
・発熱や強い痛みがあり、歩くのもつらい
・数日で体重が増えた、むくみが急に悪化した
・妊娠中や産後で、足の腫れが強い、息苦しい
足のむくみ(浮腫)とは
むくみは、皮下に余分な水分がたまった状態です。体の水分は、血管・リンパ管・細胞の間を行き来しながらバランスを保っています。ところが、血流が滞る、リンパの流れが悪い、塩分が多い、内臓の働きが落ちる、薬の影響があるなどの要因が重なると、水分が戻りにくくなり、むくみとして目立ちます。
むくみの原因は大きく2つ
1)全身性の原因(両足に出やすい)
体全体の水分バランスが崩れるタイプで、両足にむくみが出やすいのが特徴です。代表例は以下です。
・心臓の働きが低下したとき(息切れ、体重増加、夜間の咳などを伴うことがあります)
・腎臓の働きが低下したとき(尿の変化、全身のむくみが出ることがあります)
・肝臓の病気や栄養状態の低下(低アルブミン血症)
・甲状腺機能の異常
・妊娠、月経周期、更年期などのホルモン影響
2)局所性の原因(片足に出やすい、左右差が出やすい)
足そのものの血管・リンパ・炎症などが原因となり、片足だけ、あるいは左右差がはっきり出やすいタイプです。
・下肢静脈瘤、慢性静脈不全(夕方に悪化、だるさ、こむら返り、皮膚の色素沈着など)
・深部静脈血栓症など血栓が関わる状態(急な片足の腫れ、痛み、熱感が目立つことがあります)
・リンパ浮腫(むくみが引きにくい、進むと皮膚が硬くなることがあります)
・外傷(捻挫、打撲、骨折後など)や炎症(関節炎、腱・滑液包の炎症)
・感染(蜂窩織炎など:赤み、熱感、痛み、発熱を伴うことがあります)
生活習慣で起こるむくみ
病気がなくても、次のような要因でむくみは起こりやすくなります。
・立ち仕事、座りっぱなし(ふくらはぎの筋ポンプが働きにくくなります)
・運動不足、加齢による筋力低下(特に下腿の筋群が低下しやすいです)
・塩分の摂りすぎ、アルコール、睡眠不足
・体重増加、きつい靴や服、冷え
・長時間の移動(車、飛行機など)
なお、筋力が低下すると、静脈やリンパを押し上げる働き(筋ポンプ)が弱くなり、夕方にむくみが強く出やすくなります。立ちっぱなしや座りっぱなしが続く方は、足首を動かす回数を増やすだけでも改善につながることがあります。
薬が原因のむくみ(薬剤性浮腫)もある
服用中の薬によってむくみが出ることがあります。代表的には一部の降圧薬、痛み止め(NSAIDs)、ホルモン製剤などが挙げられます。自己判断で中止せず、処方医に相談してください。薬の調整で改善することがあります。
自宅でできる対策(まずはここから)
危険サインがない場合、次の対策で改善することが多いです。
・足首を動かします(つま先の上げ下げ、足首回しを1回1〜2分、1日数回行います)
・同じ姿勢を続けません(30〜60分に一度は立つ、歩く、足首を動かします)
・就寝前に足を少し高くします(クッションで心臓より少し高い位置を目安に10〜15分行います)
・ふくらはぎを温めます(冷え対策として入浴などで血流を促します)
・塩分を控えめにし、十分な水分をとります(極端な制限は避けます)
・弾性ストッキングは目的に合えば有用です(静脈うっ滞が疑われるときに効果的ですが、急な片脚腫脹や強い痛みがある場合は先に受診してください)
当院での評価の流れ
むくみは原因が幅広いため、当院ではまず問診と診察で「危険なむくみの除外」と「局所性か全身性かの見極め」を行います。
当院で確認するポイント
・いつから、どの時間帯に強いか(朝より夕方が強いか、急に出たか)
・片足か両足か、左右差の有無
・痛み、熱感、赤み、しびれ、歩行への影響
・既往歴(心臓、腎臓、肝臓、血栓の既往など)や内服薬
・外傷や運動、長時間移動の有無
整形外科的な身体診察では、関節の腫れや炎症、筋肉・腱の痛み、神経症状の有無、姿勢や歩行の特徴なども含めて総合的に評価します。必要に応じて、超音波(エコー)で軟部組織の状態や炎症所見を確認し、外傷や局所の炎症が関与していないかを検討します。
また、全身性の原因が疑われる場合や、血栓など緊急性が疑われる場合は、血液検査の評価や内科・循環器科など適切な医療機関と連携して検査・治療につなげます。原因に応じて「どこで、何を優先して確認すべきか」を整理し、過不足のない受診導線を作ることを重視しています。
治療の考え方
治療は原因により異なります。大切なのは「むくみそのものを取る」だけでなく、「原因を見極めて再発しにくい状態を作る」ことです。
・生活習慣が主因の場合:運動指導、足首・ふくらはぎの機能改善、体重・塩分管理を行います。必要に応じて理学療法士によるリハビリテーションで、下肢筋力や歩行、動作の癖を評価し、むくみが起こりにくい身体の使い方を一緒に整えます。
・静脈うっ滞が疑われる場合:弾性ストッキングの活用、下肢の筋ポンプ改善を行い、必要に応じて専門科へご紹介します。
・外傷や炎症が関与する場合:安静度の調整、アイシングや温熱、必要に応じた薬物療法に加え、回復段階に合わせたリハビリを提案します。
・全身性疾患が疑われる場合:原因疾患の治療が中心となるため、連携医療機関での評価につなげます。
よくある質問(FAQ)
Q:朝は平気で夕方だけむくみます。病気でしょうか。
A:夕方に悪化するむくみは、長時間の立位や座位による血流の滞り(静脈うっ滞)や筋力低下が関与することが多いです。ただし、左右差が強い、痛みや赤みがある、急に出た場合は受診してください。
Q:片足だけむくむのが心配です。
A:片足だけのむくみは、静脈・リンパ・炎症・外傷など局所の原因を優先して考えます。急に強くなった場合や痛み、熱感、赤みがある場合は早めにご相談ください。
Q:マッサージはしてよいでしょうか。
A:危険サインがない慢性的なむくみであれば、軽いストレッチやふくらはぎをやさしくほぐすことは有用です。一方で、急な片脚の腫れや強い痛みがあるときは、原因の確認が優先ですので先に受診してください。
最後に
足のむくみ(下腿浮腫)はよくある症状ですが、原因は生活習慣から内臓疾患までさまざまです。特に「急な片足の腫れ」「痛みや赤み」「息切れ・胸痛」を伴う場合は早めの受診が重要です。危険サインがなければ、足首運動や姿勢の工夫、塩分調整などで改善することも多いため、まずはできる範囲から始めてください。
当院(三国ゆう整形外科)では、整形外科的な身体診察に加えて、必要に応じた超音波(エコー)評価、血液検査や他科連携、理学療法士によるリハビリテーションまで一貫して対応できます。症状の背景を丁寧に整理し、原因に合わせた検査と対策をご提案します。
大阪市淀川区・阪急「三国駅」周辺で、足のむくみ、片足のむくみ、夕方のむくみ、下腿浮腫にお困りの方はお気軽にご相談ください。
参考文献
江里口雅裕, 鶴屋和彦. 発生機序から見た浮腫. 臨牀と研究. 2024; 101(10): 1189-1192.